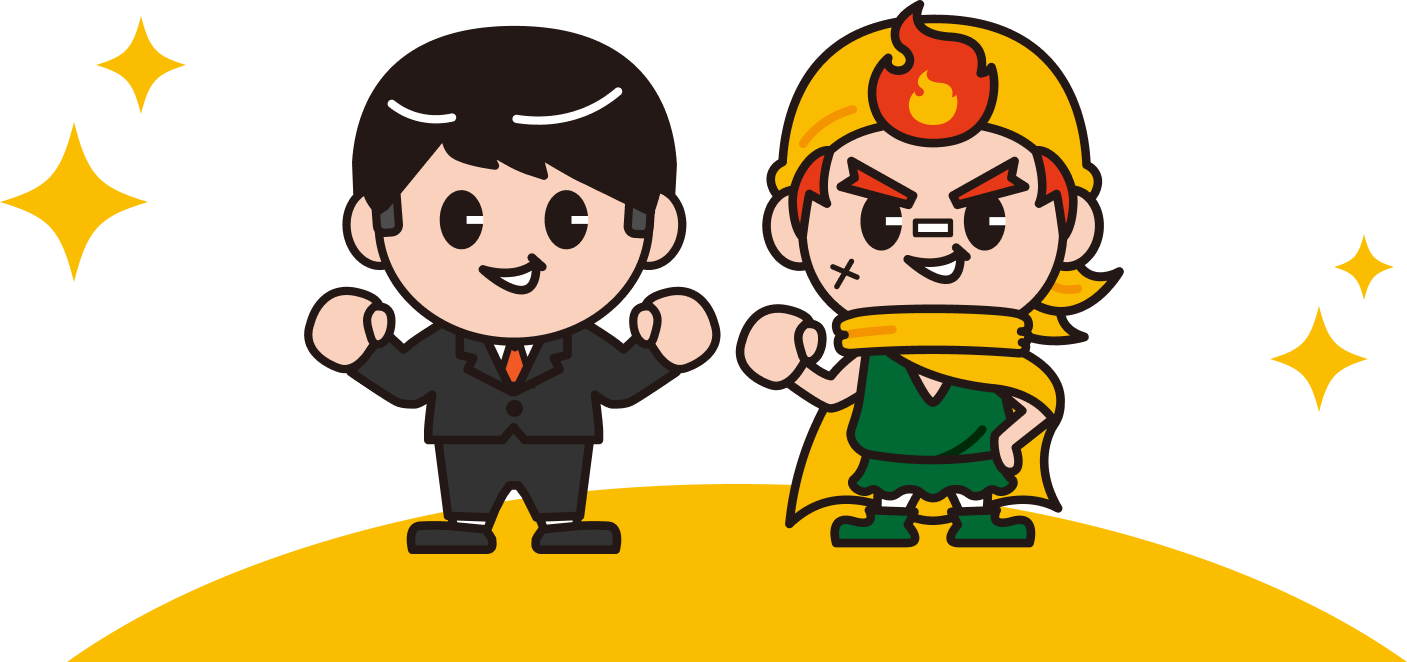【元湖南市長 谷畑英吾さんインタビュー 後編】元市長が考えるこれからの地域社会と日本とは?

今回は初めての首長OBへのインタビューとなりました。
お話をお聞きしたのは、元滋賀県湖南市長の谷畑英吾さん。
知識と経験豊富な谷畑さんだからこそ実現した濃いインタビューとなっております。これからの地域社会や日本全体のことを考えるきっかけとなれば幸いです。
本インタビュー記事は、前後編の後編になります。
前編をお読みになっていない方は是非、前編からお読みください。
【インタビュー実施日:2021年8月25日】
これからの地域社会に必要なこと
菅野:谷畑さんが考えている日本の青写真がどういうものなのかというのを本日は是非お聞きしたかったんですけれども、
谷畑さんはこれからの日本の目指すべき姿をどのようにお考えですか?
谷畑さん:そうですね。今の状態が将来にどうつながるのかがみんな見えていない、手探りの状況なわけですよね。
手探りの状況だからこそ今までの惰性でしか動かざるを得ないということなんでしょうけども、人口がどんどん減少していって少子高齢化が進んでいくっていうのは明らかなんですよ。それに対して、適応した社会をつくっていかなければならないということは常に思います。
それからもうひとつは、感染症の脅威がずっと継続していくということは明らかです。
感染症、特に新型コロナウイルスは変異が早く、ワクチンと追いかけっこになるので、スペイン風邪で亡くなる人が多かった時代とはまた違って、さらに凶悪なウイルスも出てくる可能性がある。これだけ世界が物理的に近くなった中においては、ウイルスの伝播や変異も非常に早く行われるので、それへの対応が大事になってくるわけです。
ですから、そういった意味で言うと、DXなどは早くしなければならないわけで、非接触でどういう風に社会を作り上げていくのかっていうことは非常に大事になってくると思います。ただ、非接触になると今までのような形での濃い接触の中で支えられてきた人たちをどう支えるのかということが非常に大きな課題として出てくるので、そういった課題に対して正面から対応できるような国や自治体というものを作っていかなければならないと思います。
それからもうひとつは、民主制度がどういう風に変わっていくのかということも押さえておかないといけない。
今までの日本の選挙は、大勢を集めて握手をして、そして抱き合って支持者を増やしていくというのが選挙でしたけれども、これからはまさしくWEBとかSNSとかそういったネット媒体を駆使しながら政策論争ができるような人間がでてこないといけないのだろうと思います。
だから、そういう意味でもう一度衆議院の選挙制度を中選挙区制に戻しても良いのではないのかなと思います。
要するに、当時の選挙制度改革の大元は政治資金制度改革であったわけで、お金を集めることはけしからんということであったわけですから、ネットを使ってお金を使わなくても選挙ができるような世の中になってきたのであれば、逆に小選挙区制からもう一度中選挙区制に戻して、選挙結果から捕捉されない民意ができるだけ少なくなるようにしていく。
そして、党本部に縛られて中央集権的な目線しか持たないような国会議員ばかり生み出すような社会っていうのはもう一度解体してですね、地域それぞれが力をもって独自の動きをしていきながら緩やかに連合体をつくっていくような国家像を描いていく必要があるかなと思います。

そして、そこにできる限り多くの人が参加をするということでなければ、活力というのは当然出てきませんし、新しい知恵というのは出てこない。
そういった力と知恵が出てこないような閉塞感に追い込まれているのが今の日本だと思います。ですから、地方から様々な知恵とか力を結集をして中央とやり取りをし、中央はそれをコントロールするのではなくて、調整をするという役割にもう一度立ち返らないといけない。
それを目指して地方分権改革が出てきたにもかかわらず、官邸と党本部の一極支配になっているところが今の日本の閉塞感を創り出してる大きな原因であるのかなと思います。
ですから、ヒラメ議員がたくさんできてしまい東京の方しか見ない議員が増え、地元を見てますよと言っても地元の票が欲しいがために東京の補助金や公共事業が欲しいというような議員ばかりで、制度の根幹について議論できるような議員はほとんどいないわけですよ。
それとともに霞が関においても、内閣人事局ができて高級官僚はみんな官邸の方しか見ない。
地方自治体や国民を見ずに、官邸しか見ることができないヒラメ官僚ばかりになってくるわけで、そういったところからしか出てこない政策というのは非常に薄っぺらくて、即効性が全くなくて、しかも間違ったものばかりとなっているんです。
だからすぐに朝令暮改で変えざるをえないというような状況で、まさに今、日本は三流国、四流国になりつつある。
そういう危機感は共有しないといけないのかなという気がしますね。
菅野:谷畑さんは地方発の取り組みを全国に広げるような観点もお持ちのように感じます。
地方から声を上げて国を動かしていくようなムーブメントを起こすにはどうしたら良いのでしょうか?
谷畑さん:それはですね。
市長時代から考えているのは、国が憲法第8章に違反しないように、自治体側から国に対して発信を続けることが重要だと考えています。
国が自分たちの都合の良いときには憲法に縛られるといいながら、また別のところでは都合よく憲法を無視して動こうとしていることが大きな問題なんですね。自治立法権、自治財政権、自治組織権、自治行政権、こういったものは自治体側から発信して守っていかなければならない。誰も守ってくれないですから。
総務省に言ったって総務省が守ってくれるはずないんですよ。総務省だって財務省に予算を握られているわけで。
だからこそ、首長はそこは行政の長ではなくて、政治家であれと思います。
教育現場の改革
菅野:現職首長だった時代の谷畑さんの様々な功績がある中で、一番ご自身の中で印象深いお仕事はどういったものがありますか?
谷畑さん:首長として色々行いましたけれども、首長の仕事って結局、際限ないんですよ。
どこまでいっても満足するものではないんですけれども、どれをやっても自治体が永続している限りは仕事は永遠に発生してくるので、これで完成形というのはないのですよ。
ただですね、学校現場が崩壊していたのは、立て直すことができたというのは非常に良かったかなと思いますね。
当初、ほぼすべての学校で学級崩壊を起こしていたんです。
菅野:ほぼすべてですか?すごい状況ですね。
谷畑さん:はい。うちの町は滋賀県の中でも地元出身者が教員になっている率が非常に低いんですね。
みんな働くところは一杯あるので、わざわざ教員にならなくてもという感じなので。そうするとうちの町に愛着をもって来てくれる先生というのは少なかったんです。また、校内暴力は昔からありましたけれども、そういう学習生活に指導が必要な子どもたち以外に外国籍の子どもたちが大量に入ってきてですね。
それがきっかけとして学級崩壊というのが多発したんですね。それをうけると余計転勤してくる人たち先生達がいなくなってしまったんですね。
でも実は今、県内の教員志望者で湖南市希望者がものすごく多いんです。
その理由のひとつは、障がいのある児童、生徒に対する切れ目ない支援というのをうちの町から始めて、教員側の負担を減らしました。
今は発達障害者支援法というものができましたけれども、うちの町の取り組みをそのまま法律化してもらったものです。
それから、外国籍の児童、生徒に対する支援もしっかりとできるような体制を整えながら、教員が当時モンスターペアレントに疲弊させられていたので、教員を一人で親のところに出さないようにしました。
必ずそういうところには学年主任がついていき、学年主任がだめだったら教頭がついていこうと。教頭も校長もだめだったら、教育委員会から指導主事をだせと。そのためのお金は市長部局が持っているわけですからね。
人員配置は教育委員会にはできないし、そのお金も持っていない。
だからそこは常に市長がちゃんと教育現場を見ているという状況を作っておいて、小さな問題であっても市長まで上げるようにさせました。そして、上げていないものに関しては自力でやりなさいということにしました。
そして、もうひとつはですね。わずか10万円ですけれども学校で裁量が取れる予算をつけました。
それを教育委員5人が学校から10万円争奪コンペをさせて、各学校に傾斜配分させる仕組みをつくりました。コンペの成績がよい所には13万円、もうちょっと頑張れという所には7万円しか出さないと。こういうことをやると教育委員さん達も教育現場に目を向けるし、そしてなにより学校の職員室が一体化するんですね。何としてもうちは勝ち取るぞということで、その10万円を何に使うかというコンペに一生懸命応募するわけですね。
だからそういった形で、学校が一枚岩になってチーム学校というものができたんです。
さらに、コミュニティスクールの制度を滋賀県で最初に取り入れました。
コミュニティスクールは学校運営理事会に地域の人たちが入って、公共の意思決定に地域の人たちも参画するというやり方ですけど、その裏返しとして地域学校協働本部、地域の人たちが学校に集まって学校の様々な行事の支援をする仕組みをつくったんです。
放課後のクラブ活動の指導を地域のお年寄りがするとか、運動会の準備を地域の人たちが率先して計画をするとか、そうした本部を学校の中に設けると地域の人たちが常に学校の中を出入りするようにしました。
以前、池田小学校で殺傷事件があって一時期地域を全部締め出したんですね。だから学校の中が無菌室のようになって、ウイルスひとつ入ると大感染するような状況だったので、そうではなくて地域に曝露しながらですね、社会の風もやっぱり子どもたちは受けなければいけないというような形で、地域の人たちが学校の中をうろうろするような状況にしました。
そういうことをしていると自然といじめも少なくなるし、何かあった時に地域の人たちが助けてくれるので学校も負担感が少なくなる。
そして、教員の働き方改革の取り組みもモデル事業として率先して取り組んでいたので、湖南市の取り組み自体を今度は国が吸い上げてあちこちに提示していくようになったんです。
明治以来150年、ハンコで出勤簿をやっていたのも解消して、パソコンを開けるとそれで出勤したことになるというような制度を入れたりとか、それから18時で学校の電話は切って後は全部教育委員会につなぐとかですね。
そういった形で先生たちの働き方を変えつつ、全部先生たちから何をしてほしいのか、アンケートを取りました。そして、市の教育委員会でできることは絶対やる。市でできないことは県の教育長を市の総合教育会議に呼んで、そこでいろいろ議論しながら、改善していきました。県の教育長も現場の意見を聞けるのが貴重みたいで喜んでましたね。
まあ、そういう形で、改善しているといつの間にかですね、教員希望者の殺到する町になりました。

菅野:素晴らしいですね。地方の良い仕組みがどんどん広がってほしいですね
谷畑さん:あと、退職前のベテランの先生の知識を伝える場をつくっていてですね。
きょういくげんき塾と言って、時間外に希望する若手を集めて、それを中堅・ベテランの人たちとのディスカッションを通じて悩みを聞いて、ここはこうした方がいいんじゃないのというと、我々はこうしてたよという勉強会のようなものをやっていました。また、学校の中での校種や教科ごとの研究会というのはかなり活発に行われています。
また、毎年夏休みに4泊5日ぐらいで希望する先生を東京学芸大学に留学させているんですよ。
東京学芸大学とうちの教育委員会が協定を結んで向こうの宿泊施設を無料で使わせてもらって、学会があるのでその学会で開かれているセッションの希望するところに先生たちが入るんです。それから最後は文部科学省に行ってですね。旧の文部省の大臣室の席にみんな座らせてもらって、文部科学省の若手キャリアから最新の文部科学行政についてのレクチャーを受けて帰ってくるんですね。全国に何十万人といる先生の中で、文科省の廊下を歩く先生なんていうのはほぼいない。でも、湖南市は毎年20人ずつぐらいそれを経験しているわけです。
文科行政の最新の部分はこうだとみんな理解して戻ってくるので、それをさっき言った教科ごと校種ごとぐらいの勉強グループで伝達、継承する。4日、5日なりとも現場を離れて保護者とも連絡がつかなくても良いという中で勉強して帰ってくるのでリフレッシュにもなると思います。
そういうことを行っていたら先生がわんさか集まってきたという感じですね。
菅野:何でもそうですけど、私は最後は人が大事だと思います。
教育は特に、先生達のコンディションというか、どういう状態で教育の現場にいらっしゃるかがすごく重要だと思うので素晴らしい取り組みですね。
谷畑さん:そうなんですよ。
実際にあった話ですが、別の市の山の中の中学校からうちの中学校に転勤されてきた校長先生がいて、山の中の学校だから当然地域力もあって、地域が支えていると思うじゃないですか。そして、転勤先がちょうど工業団地のど真ん中の住宅団地の中学校だったんですよ。だから、例えば校外マラソンをするのに迷惑がられるんじゃないかと思って地域の人に声を掛けたら、『いや、わしら角角に立つで』とお年寄りが大歓迎して率先してマラソンに協力してくれたみたいで。
菅野:素敵ですね.
谷畑さん:前の学校では、学校のチャイムを鳴らすだけでうるさいって周りから怒られていたと言っていましたね。
菅野:イメージと逆ですね。田舎のほうが地域の人が学校の取組みに寛容なのかと思っていました。
谷畑さん:そうなんですよね。
だから、やっぱり日頃から参画してると自分たちの学校だっていう感覚がみんな出てくるんだと思います。
そして、外国籍の方々もその中に入って一緒に支えに来てくれたりもしてますので、そういう教育現場ができたというのはひとつ大きな成果だったと思います。
谷畑さんの芯の強さについて
菅野:最後に、谷畑さんからは自分の信念をぶれずに、周りの空気にも流されずに貫き通すような意志の強さを感じるんですけれども、そういうものを政治家として一人の人間として持てているのはどういうところに要因があるのでしょうか
谷畑さん:そうですね。
小さい頃から歴史をずっと読みこんできたので、一回この国は滅亡してるじゃないですか。
滅亡の経過を見ていると、やっぱり空気が滅亡させているので、空気が大嫌いなんですよ。ただ空気は読めますから、別にKYではないんですけれども、空気は読んでいる中でまずいというタイミングに水を差す。
KYという人は空気を読めてない所で水を差すからみんなに嫌がられるんですけれども、空気を読みながらこの時点だったら空気は消えるだろうという時に水を差すということを常にやらなければいけないなということを自分に課しているだけなんですね。
菅野:なるほど。歴史を知っているからこそ今の状況を俯瞰して見ることができて、空気を読んだ上であえて水をさしているというような感覚なんですね。
谷畑さん:そうです。だからみんな保身に走って空気にがんじがらめになってしまうので、嫌がられる役割ではありますけれども、誰かがやらなければいけないので。
最後に
いかがでしたでしょうか。
常に歴史的な大局観を持ち、自らが信じた成すべきことをする。言葉にすることは簡単ですが、ぶれずに貫き通すことは誰にでもできることではありません。歴史的にも転換点にある現代だからこそ誰しもが持つべきマインドを学ばせていただきました。
貴重なお話をありがとうございました!