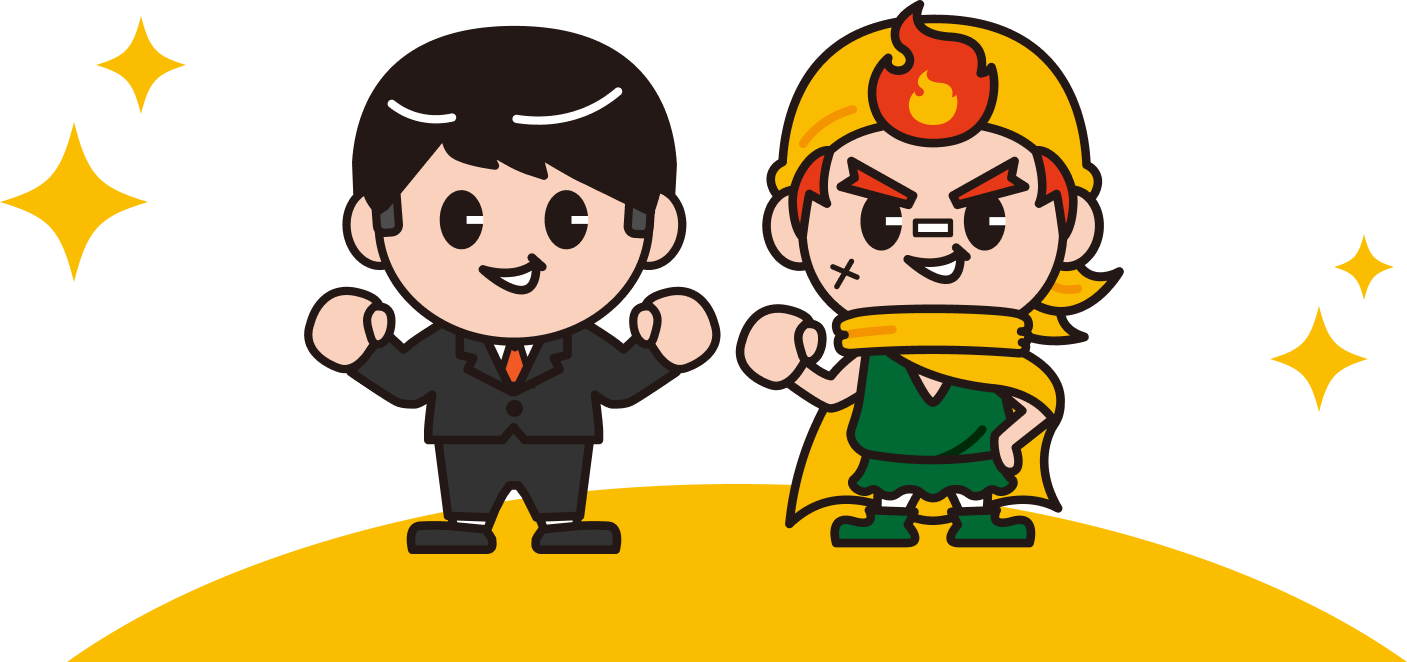【川俣町長インタビュー】里山の景観を大事に守りながら、少子高齢化に取り組む

今回の首長インタビューは、福島県川俣町の藤原一二町長。
川俣町は原発事故による避難者や高齢化により、この10年で少子高齢化が激しく進んだそうです。
以前のような元気のある川俣町を取り戻すために取り組まれている対策や、職員の皆様に伝えたいこと、をお伺いしました。
昔のように元気のある川俣町を取り戻したい
町長を志した経緯を教えてください
町長への立候補が、復興からの10年を総括して新しい計画を作るタイミングで、でした。
川俣町は少子高齢化が激しく進み、この10年で約4000人の人口が減りました。震災での避難の影響もありますが、高齢化率が42%と高齢化も急激に進んでいます。
なんとかして昔の元気ある川俣町を取り戻したい、その思いで「変えよう!川俣」をキャッチフレーズに、顔の見える優しいまち作りを進めてきました。
元々は役場の職員をなさっていたんですね。
はい、職員を40年くらいやりました。その後は医療と福祉分野に勤めていました。そこで町民から強く立候補を求められまして・・・年齢的にも若いとは言えませんが、みなさんの熱い思いに後押しされました。
特に川俣町は、東日本大震災で町の3分の1、農村地帯だけが避難しました。避難したエリアは、この10年でハード面も整備されていますが、避難をしなかった旧川俣町の人口も減りました。この10年で空き家や空き地が増えましたが、そこを何とかしないと本来の復興再生した川俣町にはならない。
その点も町民の皆様からかなり強い要望があって取り組んでいます。

特に力を入れている事業はありますか。
国の支援(福島再生加速化交付金)を受けながら、働く場所の確保に力を入れています。避難した方々に戻ってきてもらおうと考えた時、働く場所や住まいを確保することは最優先です。工業団地造成を行い、新しい企業に入っていただいたり、地元の企業が工場を拡張する計画を進めています。
あとは、少子化と人口減少の対策ですね。
子どもが少なくなってきているとはいえ、一番大変なのは、親御さんたちの経済的な負担です。
子どもをのびのびと育てられるまちづくりを第一に考え、そして親御さんたちの財政負担を極力少なくするために、この4月から小中学校の給食無料化、制服の無償支給を行っています。来年度からは0歳から5歳児までの給食無償化と、保育料の全額支援を考えています。
そして、働く場所の確保と住む場所の確保、この3点を目標にして、少子化人口減少対策に挑戦しよう、と取り組んでいます。
川俣の特産品や、現在の産業を教えていただけますか。
川俣町は古くから養蚕業が盛んで、絹織物の町として栄えてきました。道の駅も「シルクピア」という名前です。また、地域ブランドで農水省のGI認証をいただいた、川俣シャモの飼育や生産が盛んです。花卉(お花)も、トルコギキョウや小菊の栽培に震災前から取り組んでいました。震災後には近畿大学の支援を得て、南米産のアンスリウムという花の栽培を始めました。アンスリウムは暖かい地方で咲く花ですが、川俣町ではハウス栽培を行い、リサイクルのポリエステル培地を土の代わりに使っています。SDGsの事業推進で、取り組んで6年ほど、町内12の農家さんで50万本の生産を目標に、川俣町の新しい事業になっています。
新たに誘致した企業さんの研究所では、野菜の苗用のワクチンを研究しています。虫や病害虫、カビから守るということで、その研究が川俣町で始まりました。
町民の皆様に信頼される役場づくり
職員の皆さんに伝えたいことや日々の業務で大切にしてほしいことはありますか。
町民の皆様から信頼される役場を作りましょう、と常々言っています。
町民に信頼されて初めて「いい町」と言えると思います。簡単なことですが、「お客さまが来たらちゃんと挨拶しましょう、挨拶をもらったら返しましょう」ということからはじめています。
あとは窓口業務で「わからなかったら間違ったことは絶対答えない。必ず上司に相談する」そういうことをお願いしたい、と常に言っています。
相談・連絡・報告、これをきちんとやってもらう。「今年は予算がないから駄目です」と、窓口で町民の方を帰してしまう、それでは困るわけです。予算がない場合はどうするのか、いつまで待てばできるのか、ということも返答ができるような役場を作っていきたいです。
どんな組織でも、信用を得られないといい仕事はできないと思っています。
その点は職員の皆さんにも理解していただきたいと思います。

最近、役場の方のお話しをお聞きすると、結構体制を絞っている役場も多くて、ただ仕事量は増えているそうですが・・・
わたしも十数年ぶりに役場に戻りましたが、業務のほとんどはパソコンでやれるからもっと余裕があるんだろうな、と思ったらとんでもない、全然違っていました。特にこの3年、コロナ禍もあり、それに加えて昨年と今年の2回の地震、川俣は去年の被害がひどかったです。さらにその前に2019年の水害と自然災害も続きました。いろいろ重なる厳しい町長のスタートでした。
元々役場職員のご経験もあり、今は役場を率いる立場になられましたが、組織運営やマネジメントで意識されていること・取り組まれていることはありますか。
今年4月から政策推進課という課を作りました。各課から寄せられた要望を、町長直轄でやれるような体制を作りました。
そこで意思決定をして、スピードアップを目指しています。
役場内に横串を刺すような機能が必要ですよね。
川俣町くらいの人口規模の場合、予算総額は多くても60億円ぐらいです。
ですが、復興に関する交付金が多く入ってくるので、常に予算が100億円を超えています。
その予算を執行する業務量を考えれば、職員はかなりの仕事量だ、とわかります。
そういう中で、環境やまちを整備しても住む人がいなくなり、学校や幼稚園が空いてしまう。
空き施設の活用にはいろんな民間のお力も必要ですし、地域の方々との話し合いが必要です。
担当部署では、先進事例地の視察や地域での意見交換会を実施しながら、有効な利活用について検討を進めています。
若い人に来ていただくための、まちの魅力づくり
最後に、今後に向けた抱負で、まだお話になられてないことがあればお願いします。
若い人たちに来てもらう、住んでもらうには魅力作りも必要です。
川俣町にはさまざまなイベントがあって、その中でも中南米音楽祭(コスキン・エン・ハポン)が有名で、昭和50年から続いています。
今年(2022年)は規模を縮小して開催します。毎年全国から200団体ぐらいが参加するイベントですが、交流人口・関係人口拡大のためには必要ですね。
そして、川俣町には、自然豊かな里山があり、清らかな水があり農業が繁栄してきました。
広瀬川沿いに街が発展し、絹織物も盛んになりました。
里山の麓で発展してきたこの町の自然・景観は何としてでも残していかなくてはいけない、と思っています。自然は一度破壊されたら元には戻りませんからね。
おわりに
若者が定住し子育てがしやすいまちづくりや、新たな産業育成等にも積極的に取り組んでいる川俣町。
伝統産業である絹織物や川俣シャモ、トルコギキョウ等の地域資源の豊富さも印象的でした。
起業文化が盛んな歴史を踏まえて、もう一度チャレンジする町民を増やしていく可能性を感じたインタビューでした。
貴重なお話しをお聞かせいただき、ありがとうございました!