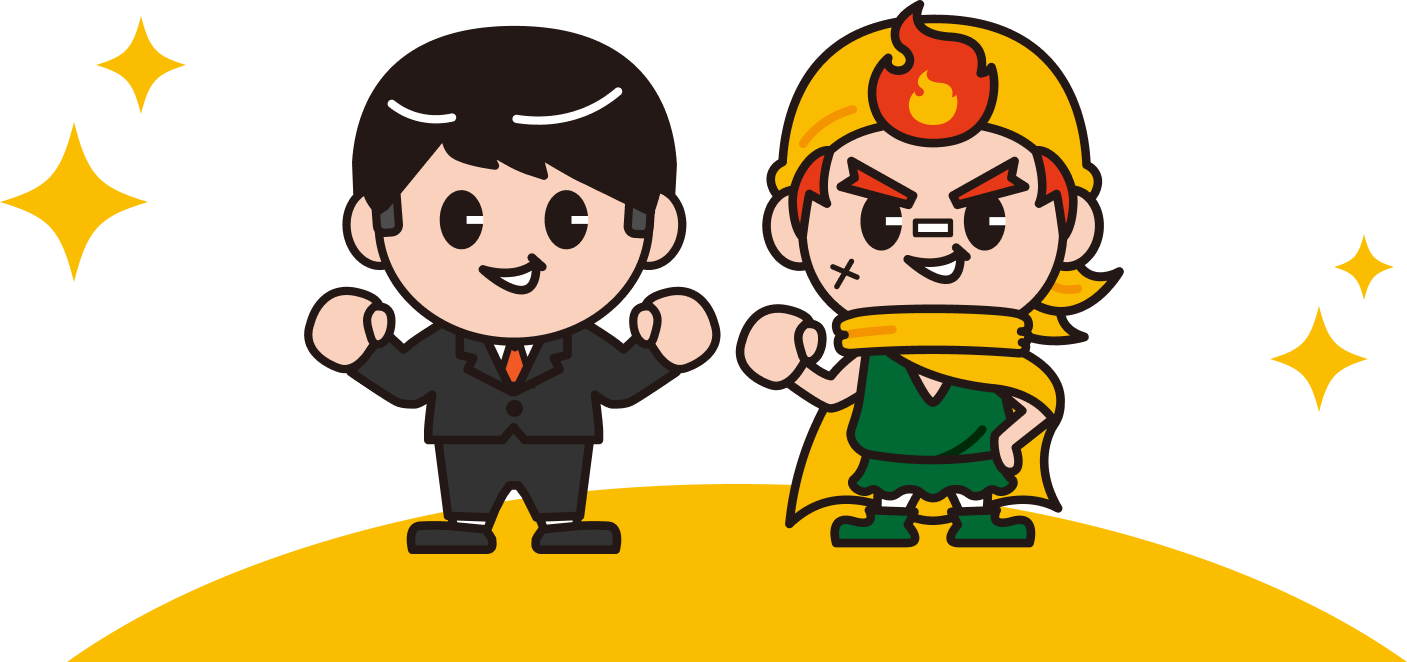株式会社全力優 創業ストーリー(前編)

すべての始まりは「わるだくみ」から

「世の中を明るくする良いわるだくみを」
これは、株式会社「全力優」の企業理念だ。代表取締役の菅野永は、自らのキャリアを「回り道だった」と笑う。
銀行員、北海道庁職員、ベンチャー企業のサラリーマン、そして経営者。一見すると脈絡のない経歴は、実は一本の線で繋がっている。社会貢献という「青臭い理想」 と、子どもの頃から変わらない「楽しそうだからやってみたい」という気持ちだ。
2025年4月、菅野は会社を「全力優」に社名変更した。その背景にはどのような思いがあったのか。そして、全国の首長(市長・町長・村長等)に無料で届けられる「首長マガジン」は、どのようにして生まれたのか。
北海道で目の当たりにした、地方の現実から話は始まる。(インターン・千葉小鈴)
天職を探した20代。銀行員を辞め公務員へ
「正直、仕事はそこそこで、プライベートを充実させたかったんです」
菅野は大学卒業後、地元の地方銀行に就職した。学生時代に熱中したモトクロスのレースを続けるには、地元・仙台が良い環境だった。ただ、社会に貢献したいという想いは持ち続けていた。地球環境問題に関心があり、大学で農学部を選んだのもその理由だった。
銀行員の日々は、その想いとのギャップを感じさせた。「自分はビジネスより、公の世界が向いているのかもしれない」。そう考えて公務員への転職を決意。北海道庁の秋採用で、社会人としてやり直すことにした。
配属されたのは、空知(そらち)地方の「市町村課」。道内市町村の行財政運営をサポートする部署だ。担当エリアには、財政破綻した夕張市があった。
地域に貢献したいという気持ちとは裏腹に、課題は大きかった。新社会人が一人でどうにかできる問題ではない。「役に立ちたいけど、役に立てない」。もがけばもがくほど空回りし、評価もされない。もどかしさだけが募った。
「このままでは、自分が成長できない」
2年弱で、彼は再び転職を決める。安定した公務員の職を辞め、自分を鍛え直すために、仙台のベンチャー企業に入った。
「地方創生」を契機に経営者の道へ
転職先は、ベンチャー企業を支援する会社だった。そこで菅野が働き始めた頃、第二次安倍政権が「地方創生」を打ち出し、全国の自治体が新たな取り組みを模索し始めていた。
「うちの会社に、自治体から『起業家を支援したい』といった相談が増えたんです」
ベンチャー投資という金融事業と、自治体のプロジェクトを回していく仕事。その違いから、会社は自治体向け事業を「分社化」することにした。その新会社の経営者を、菅野が任されることになった。
北海道庁で地方の現実を見てきた経験が、ここで活きてくる。「自治体の課題解決をビジネスにしたい」という想いがあった。日本の自治体は1788あるが、抱える課題には共通点が多い。地元の仙台からでも、日本中の自治体に展開できるサービスがつくれるはずだ。
ただ、具体的な事業アイデアはすぐには見つからなかった。
「何をやったらいいんだろうって、色々考えてやってみたんですけど、うまくいかなくて」
試行錯誤が続くなか、シンプルな問いに立ち返った。「まず、自治体の経営者である『首長』が、何に困っているのか。それを知ることから始めよう」。
「首長の孤独」との出会い

その日から、菅野は採算度外視の活動を始めた。全国の首長にアポイントを取り、「まちづくりへの想いを聞かせてください」とインタビューして回る。その内容を無料でブログ記事にして発信する。事業ではなく、ボランティアだ。目的は、首長たちが抱える課題を直接聞くことだった。
インタビューを重ねるうち、多くの首長が同じ悩みを口にしていることに気づいた。
「首長の仕事って、誰も教えてくれないんだよね」
最初は信じられなかった。支えてくれる職員はたくさんいるではないか、と。だが、ある首長の話が、その認識を変えた。
「首長になった初日だよ。幹部職員がバタバタっといきなり辞表を叩きつけてきてさ」
自らの就任と同時に幹部職員が一斉に辞めていった。職員は必ずしも味方ではない。議会の反発もある。4年という短い任期の中で成果を出さなければならない。外から来た「雇われ社長」のようなもので、そのプレッシャーと孤独は大きかった。
1788の自治体のトップが、それぞれ同じようなことで悩み、孤軍奮闘している。この「経営者としての課題」を解決することこそ、自分がやるべき事業ではないか。
同じ頃、のちに「首長マガジン」の発行人になる、元滋賀県湖南市市長・谷畑英吾氏と出会った。二人は意気投合し、現職の首長が参加できる「首長の学校」を始める。
手応えはあった。ただ、ボランティアでは続けられない。「いいことだとしても、続けるためには稼がないと意味がない」。
首長の課題を解決しつつ、ビジネスとして成立させる。その二つを両立させるアイデアを模索した末に生み出されたのが「首長マガジン」だった。
(後編に続く)